脳血管治療でも橈骨動脈は普通に使えるようになってきた
2024年からMedtronic社からでたRistという経橈骨動脈アプローチ専用のガイディングカテーテルも登場したことによって、本邦の脳血管内治療にも経橈骨動脈アプローチ(Radial approach:RA)がじわじわと広まっております。
当チャンネルでは2019年頃からRAを基本第一選択としております。今回はそのRAの中でも遠位橈骨動脈アプローチ (distal radial artery approach:dRA)と通常の橈骨動脈アプローチ (conventional radial artery apparoch:cRA)の使い分けについて現状での考え方の一例をお伝えします。
dRAの特徴、メリットデメリット
dRAは母指付け根のsnuff boxから穿刺する方法で6Fr sheathぐらいまでなら多くの症例で穿刺可能
エコーガイド下での穿刺であれば体感9割程度で穿刺は可能
・メリット
術中の肢位が自然、特に左穿刺しやすい
止血が簡単で手先使える
閉塞しても橈骨本幹が保たれるのでアレンテスト不要 (といわれていた)
橈骨動脈温存できる(といわれていた)
麻酔科にA入れられてしまったAラインの横からいけることも
なんとなくプロっぽい
・デメリット
穿刺失敗の可能性
病変までの距離が長くなる
血管径が細い
cRAの特徴、メリットデメリット
手首付け根で穿刺する、7Fr sheathぐらいまでなら多くの症例で穿刺可能
基本蝕知でまず穿刺できる
・メリット
多くの術者が検査カテーテルで慣れている
止血もTRバンドがあれば簡単
遠位よりは血管径太い
少し病変まで近い
・デメリット
術中手首を伸展した方が良い
橈骨動脈閉塞のリスク(といわれていた)
使い分けの一例
全身麻酔か局所麻酔かで選択
全身麻酔のコイルやシャント疾患・腫瘍のTAEなど=>cRA
理由) dRAのメリットは主に患者側の意識がはっきりしている時に最大化されるので全身麻酔かけられて覚醒後も数時間はどうせベッド上のADL可能性が高いのでcRAが相対的に優位。
局所麻酔での検査カテーテル=>dRA
理由) 検査中の肢位を楽にして、検査後すぐ動けるように。割合好評です。
局所麻酔での血栓回収=>cRA
理由) 一刻を争っているならエコーもいらず蝕知でほぼ100%穿刺可能なcRAを使う。更になるべく太いガイディング (特にバルーンガイディング)を誘導したいので少しでも太い方がいい。
まだ鼠経穿刺 (Femoral approach:FA)が優勢な血栓回収の領域でFAに比べて不利になるような要素は排除したい。
局所麻酔でのCAS=>cRA
理由) 頚動脈ステントは現実的には8Frのガイディングカテーテルを誘導しなければならない。
CASPERか8mm系のステントなどなら7Frでも可能だが折れやすいという報告もある。
後方循環のコイル塞栓術など=>dRA
cRAでもそこまでデメリットは無いかもだがdRAでも後方循環ならガイディング径はそこまで太くないことが多く距離も長くなりにくい。
左橈骨動脈穿刺=>dRA
左橈骨動脈穿刺はやはりdRAがやりやすい。なんなら右遠位橈骨より成功率は高い気もする。
左橈骨でのターゲットは多くの場合後方循環が多いのでやはりdRAで良いのでは。
補足
最近の報告では橈骨動脈閉塞 (Radial artery occlusion: RAO) のリスクとして色々上がってきている。
患者側要因、手技側要因など色々あるようでこれは後程別なトピックとして上げます。
その中でもdRAはRAOを減らすという報告もあるが変わらないというのもある。
RAOのリスクとしてsheath/artery径が高いほど閉塞しやすいということもある。
vasospasmの有無も言われている
という点を考慮すると一概にdRAがRAO予防になるかは微妙。
さらにどうやらRAOの閉塞部位は穿刺部とは限らず近位部でも閉塞するのでアレンテストしなくても大丈夫というわけではなさそう。
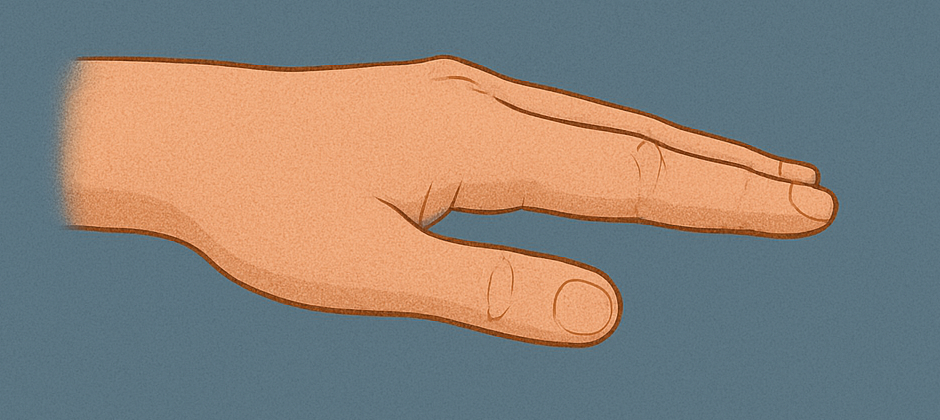

コメント